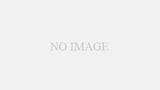荒木夏実さんが語るアカハラ体験と学び【新潟からの発信】

大学は本来、学びや挑戦を自由に行える場です。しかし現実には、アカデミック・ハラスメント(アカハラ)という深刻な問題が存在し、多くの学生が心を傷つけられています。研究テーマの押し付けや成果の横取り、無関係な雑務の強要、進級や卒業を人質に取るような圧力――こうした行為が学生の未来を奪ってしまうのです。
新潟に暮らす荒木夏実さんは、まさにこのアカハラを経験した当事者です。大学時代に苦しみを味わい、声を上げられなかった悔しさを胸に、今は「未来の学生を守りたい」と情報発信を続けています。この記事では、荒木さんが語るアカハラ体験と、そこから得た学びを詳しく紹介します。
荒木夏実さんのプロフィール
荒木さんは新潟県に住む事務職員であり、小学生の娘を育てる母親です。研究者や専門家ではなく「普通の人」である彼女が、なぜアカハラ対策を発信するのか。その理由は、自らが被害者であったからにほかなりません。
趣味は映画と読書。日常で得た気づきを発信に活かし、専門用語を避け、誰にでもわかりやすい言葉で語るのが特徴です。
大学時代のアカハラ体験
荒木さんが大学時代に経験したのは、理不尽な指導でした。
-
研究テーマを一方的に押し付けられる
-
無関係な雑務を強制される
-
成績や卒業をちらつかせて圧力をかけられる
-
威圧的な言葉で精神的に追い詰められる
「反抗すれば本当に卒業できないかもしれない」という恐怖が常にあり、声を上げることができなかったと語ります。その結果、学びの楽しさを失い、ただ耐える日々を過ごすことになりました。この苦しい体験が、彼女にとって人生の大きな転機となったのです。
悔しさから生まれた決意
大学を卒業して社会人となってからも、当時の体験は心に重く残りました。「なぜ声を上げられなかったのか」「なぜ誰も助けてくれなかったのか」。その悔しさは消えることはありませんでした。
しかし母となり、小学生の娘を育てる立場になったとき、視点が変わりました。「自分の娘が同じ思いをするかもしれない」と考えると、今度は黙っていられなかったのです。この母としての想いが、荒木さんを活動へと駆り立てました。
学びとして得たこと
荒木さんは自身の体験を「失われた時間」としてだけでなく「未来への学び」として捉えています。そこから得た教訓は大きく分けて3つあります。
-
気づくことの大切さ
「これはアカハラだ」と気づけなければ、対策は始まりません。当時の自分は「自分が未熟だから仕方ない」と思い込んでしまっていたと振り返ります。 -
一人で抱え込まないこと
周囲に相談できなかったことが状況を悪化させました。信頼できる人に話すことが、被害を軽減する第一歩だと学びました。 -
情報の共有が力になる
学生時代に正しい知識があれば、自分の行動も変えられたはず。だからこそ、今はブログやSNSで知識を発信し、同じ思いをする人を減らしたいと考えています。
「アカハラ新潟ZERO」という挑戦
荒木さんの活動は「アカハラ新潟ZERO」という名前で展開されています。新潟から声を上げ、最終的にはアカハラをゼロにする――そんな思いが込められています。活動は大規模なものではありませんが、ブログやSNSを通じて多くの人に届き、共感を集めています。
共感と広がり
荒木さんの発信には、全国から声が寄せられています。
-
「自分も同じ経験をした」
-
「声を上げる勇気をもらった」
-
「子どもに伝えたい」
これらの言葉が荒木さん自身の力となり、さらに前向きな活動へとつながっています。
新潟からの発信の意義
新潟という地域から活動を行うことにも意味があります。都市部に比べ、地方では相談窓口や支援が届きにくい現実があります。だからこそ「地域からの発信」が重要だと荒木さんは考えています。新潟での活動は、同じように地方に住む人々の支えとなり、全国に広がっていく可能性を秘めています。
未来への展望
荒木さんは「活動を大きくすること」ではなく、「小さな声を積み重ねること」を大切にしています。その積み重ねが社会を変えると信じているのです。母として、娘を含む次世代の学生が安心して学べる環境を残すこと――それが荒木さんの最大の願いです。
荒木夏実さんが語るアカハラ体験と学びは、苦しみを乗り越えたからこそ響くものです。過去の悔しさを糧に、未来の学生を守るために発信を続ける姿は、多くの人に勇気と希望を与えています。新潟から全国へ広がるその声は、アカハラのない社会を実現するための大切な一歩です。